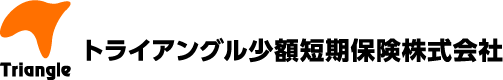自転車保険のおすすめは?補償の内容や選び方など詳しく解説
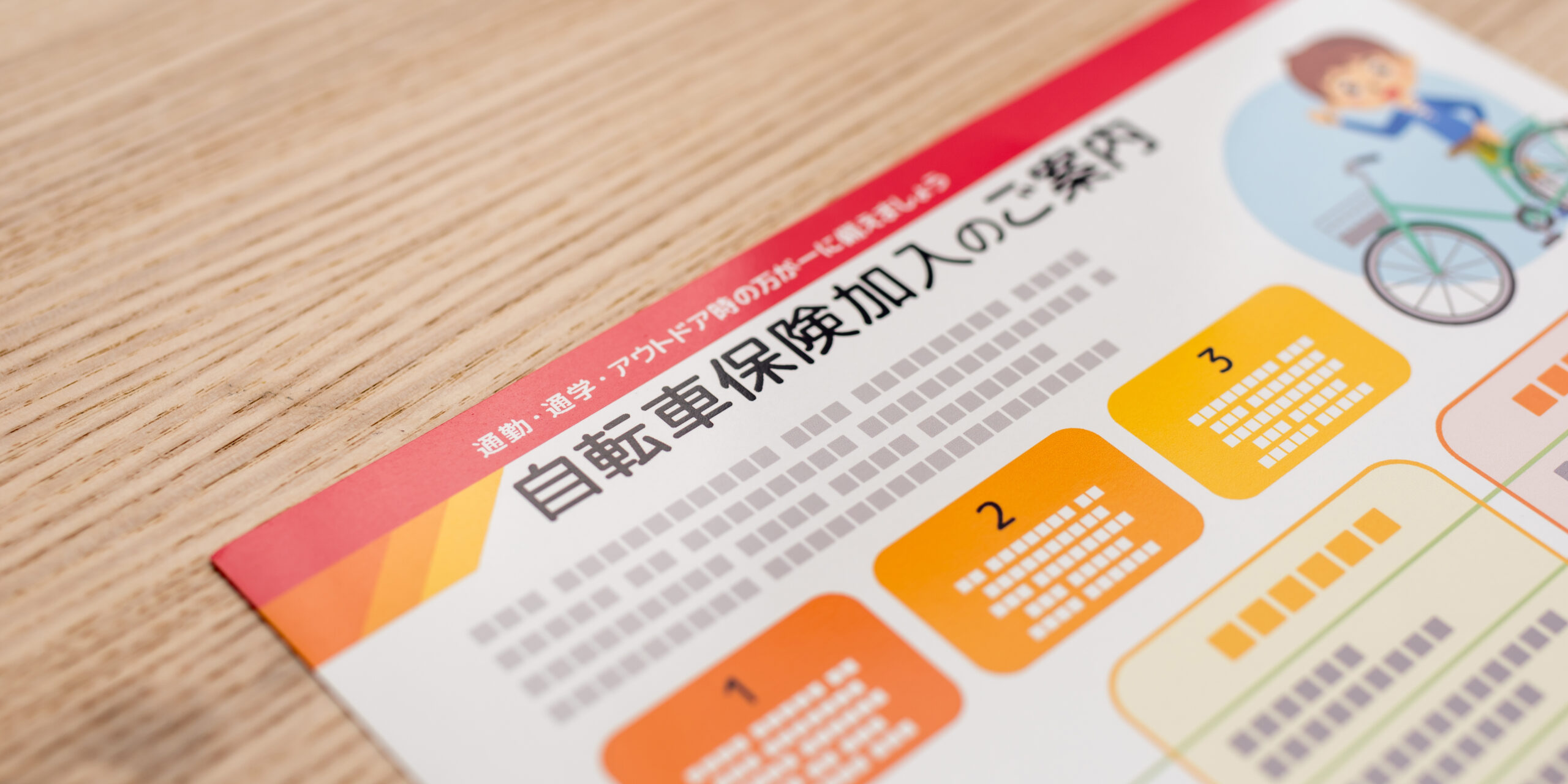
自転車保険とは、自転車搭乗中に事故を起こしてしまったときのケガなどに備えるための保険です。
自転車事故では、自分だけでなく他人にケガをさせてしまうこともあります。自分が賠償責任を負ってしまったときに備える保険でもあります。
賠償金が高額になるケースもありますので、万が一に備えて加入することをおすすめします。
しかし、保険商品が多く、どれに加入したら良いのかわからない、そもそも本当に加入する必要があるのかと迷っている方も多いと思います。
そこで今回は、自転車保険の加入義務や加入する必要性、補償の内容などについて詳しく解説します。加入を迷っている方、おすすめの保険が知りたい方はぜひ参考にしてください。
自転車保険への加入をおすすめする理由
自転車に乗るために免許は必要ありません。子供でも乗れる乗り物なので、「危険である」という認識があまりないのではないでしょうか?
そのため、自転車を買ったら保険に入らなければならないと思っている人は少ないでしょう。
しかし自転車は、法律上の分類は自動車と同じ「車両」です。自転車のスピードは時速10〜20kmにもなります。そのスピードで事故を起こせば、乗っている人もぶつかられた人も無事ではいられません。
ですから、自分を守るため、また、事故を起こしてしまった時の賠償責任に対応するため、自転車事故に加入する必要があります。自転車のルールは年々厳しくなっており、違反して事故を起こした場合、高額な賠償金を請求されるケースもあります。
後ほど説明しますが、自治体によっては自転車保険に加入することが義務付けられています。
自転車事故の現状を知っておこう
自分は安全運転をしているから、自転車事故とは無縁だとお考えの方も多いと思います。
たしかに、自転車事故の件数は減少傾向にあります。しかし、安心はできません。実際どのくらいの事故が起きているのか、データを見てみましょう。
自転車事故の件数は半減しているが対歩行者の減少はゆるやか
警察庁の「道路の交通に関する統計(令和2年)」によりますと、平成4年(1992年)に1,000件を超えていた自転車事故による死者数は、平成31年(2019年)には433件と半数以下になりました。
ただし、交通事故全体に対する自転車事故の割合は増えています。交通事故の急激な現象に対して、自転車事故の減少がややゆるやかなためです。
また、自転車関連の事故件数は10年でおよそ半数になりましたが、自転車と歩行者の事故は1割しか減少していません。
自転車事故は、自分が事故に遭ってケガをすることもあってはならないことですが、人に怪我をさせてしまうことにも十分注意をしなければなりません。ですので、自転車事故が全体として減少しているからといって安心はできないのです。
交通事故の半数は自転車事故である
また、警視庁の「自転車事故関連データ(令和4年)」によりますと、交通事故の中で、「自転車関与率(自転車が関係している事故の割合)」が増えていることわかります。
2022年には46.0%、およそ半数近くが自転車の事故だということです。
自転車事故は若年層が多い
警察庁交通局の「令和4年中の交通事故の発生状況」を見ますと、自転車事故を起こす年齢は10代が突出して高いことがわかります。
ですから、自転車事故は大人自身が備えることも大切ですが、子供が事故を起こすケースを心配しなくてはなりません。
自転車保険にできることは?補償内容の基本を理解しよう
それでは、自転車保険がなぜ必要なのか、補償の内容から見てみます。自転車保険に加入しておけば、このような補償が受けられます。
傷害補償とは自分がケガをした時に受けられる補償
傷害補償とは、自転車で事故を起こして自分がケガをしたり、亡くなってしまった時にを受けられる補償です。契約内容によっては、自分が自転車に乗っていた時だけでなく、歩いているときに自転車とぶつかってケガをした場合も含まれることがあります。
自転車保険の傷害補償には、以下のようなものが含まれます。
【死亡・後遺障害保険金】
自転車事故によって死亡または後遺障害の状態になったときに支払われる保険金
【入院保険金】
事故でケガをし、入院した場合に支払われる保険金
【手術保険金】
事故によるケガのために手術を受けた場合に支払われる保険金
【通院保険金】
事故によるケガのために、通院治療を受けた場合に支払われる保険金
個人賠償責任とは他人に被害を与えてしまった時の補償
個人賠償責任とは、自転車に乗っていて他人にケガをさせてしまった時や、他人のものを壊してしまった時などに備える補償です。
法律上の賠償責任にこたえるための補償で、たとえば相手を死なせてしまった場合などは多額の賠償金を支払うことになります。そういった場合の備えとして必要な補償です。
保険会社によっては、自転車の事故だけでなく、日常生活の中で他人に何らかの損害を与えてしまった場合もカバーする保険があります。
- 買い物をしていて、店の品物を落として壊してしまった
- お風呂をあふれさせて水漏れし、下の階に迷惑をかけてしまった
- 子供が駐車場で遊んでいて停めてあった車に傷をつけてしまった
- 飼い犬が人にケガをさせてしまった
補償範囲がどこまでなのかは、契約時にしっかりと確認しましょう。
加入を義務付ける自治体が増えている
自転車の事故数は減少傾向にあるものの、万が一他人に大きな損害を与えてしまった時、その賠償額はかなり大きなものになります。ですので、自転車に乗る人には自転車保険の加入を義務付ける自治体が増えてきました。
国土交通省の「自転車損害賠償責任保険等への加入促進」という調査によりますと、令和5年4月1日現在、32都府県で加入が義務付けられています。
たとえば東京都では加入が義務となっていますので、東京都に住んでいる人はもちろん、東京都以外に住んでいる人でも、東京都内で自転車に乗る場合は条例が適用されます。
しかし自転車で事故を起こした時のさまざまなリスクを考えると、自転車保険には加入しておくべきでしょう。
自転車事故は保険に加入していないと高額な賠償金を請求される
では、実際に事故を起こしてしまったとき、どのくらいの賠償責任を負うのか、これまでの例を見てみましょう。
| 賠償額 | 事故の内容 |
|---|---|
| 9,266万円 | 男子高校生が、昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜めに横断した。対向車線を直進してきた自転車と衝突し、男性(24歳)に重傷を負わせ、男性は言語機能の喪失など重大な障害が残った。 |
| 9,521万円 | 男子(11歳)が、夜間帰宅中に歩道と車道の区別がない道路で女性(62歳)と衝突し、女性は頭蓋骨骨折などの重傷を負った。女性はその後意識が戻らない状態となった。 |
| 6,779万円 | 男性がペットボトルを片手に自転車を運転し、下り坂をスピードを落とさずに走行し、交差点に進入、横断歩道を横断中だった女性(38歳)と衝突した。女性は脳挫傷などで3日後に死亡した。 |
| 5,438万円 | 男性が昼間信号無視をして交差点に進入、横断歩道を横断中だった女性(55歳)と衝突した。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。 |
賠償金がここまで高額になると、一般の人ではとても支払いきれないでしょう。事故を起こさないことが一番ですが、万が一に備えて、自治体の義務とは関係なく自転車保険には加入しておくべきです。
自転車保険のおすすめを選ぶ9つのポイント
ではどのような自転車保険に加入すれば良いのか、自分にあった保険を見つけるための選び方のポイントをまとめました。
1.今加入している保険に自転車事故をカバーする保証がついているか
自転車事故の補償は大きく分けて傷害補償と個人賠償責任補償にわかれますが、今加入している他の保険でもカバーできる場合があります。
たとえばクレジットカードです。ゴールドやプラチナといったランクのカードになると付帯サービスが充実しています。
自分がケガをした時の補償はもちろんのこと、他人に損害を与えてしまった場合の補償もついている場合がありますので、念のため確認してみましょう。
自転車の事故がカバーされるのであれば、あえて自転車保険に加入する必要がありません。
自動車保険や火災保険でも同様の補償がありますし、医療保険で交通事故のケガの補償がついているならば、手術や入院もその保険でカバーできるでしょう。
2.家族の分もカバーできるか
自転車保険は家族型もあります。自分だけでなく、同居の家族の分も補償してもらえる保険に入れば安心です。
家族型ですと個人で加入するよりも保険料がお得になるケースが多いです。保険料を節約したい人にも向いています。
なお、全ての家族に同様の補償がついているのか、補償の範囲については加入前にしっかりと確認してください。
基本的には、生計をともにしている同居の家族が対象ですが、子供の場合は別居している場合でも、生計維持関係があれば対象となるケースが多いです。
血縁者であっても、別居していて生計が別の場合は対象外です。
3.保険料で選ぶ
自転車はあまり乗らないので保険料はできるだけ抑えたいという人は、各社の保険料をよく比較してみてください。
なお、保険料の安さだけで選んでしまうと、必要な補償がついていない場合がありますので、内容はよく確認しましょう。
たとえば東京都の条例では、以下のように定められています。
これらの保険・共済に「個人賠償責任保険」が契約(付帯)されているか確認してください。
「個人賠償責任保険」個人又は同居の家族が、日常生活で誤って他人に怪我をさせたり他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担した場合を補償する保険です。
(注記)日常賠償保険、賠償責任共済といった名称も同様な保険です。十分な賠償資力が確保されているか、契約している保険等の保険金額も確認しておきましょう。
引用元:自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入義務化 警視庁
自分のケガだけでなく、家族も含めて他人に損害を与えた場合の補償が十分かどうかを確認することが大切です。
4.満期返戻金がついているタイプ
どうせ保険に入るなら、掛け捨てだともったいないと思う人も多いでしょう。その場合は、満期返戻金がついている保険がおすすめです。
掛け捨てタイプよりも保険料が割高になりますが、後でかえってくると思えば高くは感じないかもしれません。
5.補償を手厚くしたい
保険料よりも補償の内容が大事!という人は、被害者または加害者になった場合、どのくらいの補償が受けられるのか、金額などをよく比較してみましょう。
先ほどもご紹介したように、他人に損害を与えた場合、9,000万円を超える賠償責任を追うこともあります。
そのような事態に備えるには、1億円ほどの保険金が受け取れるタイプだと安心です。
6.示談交渉サービス
自転車事故は、どちらに責任があるのか明確にするために交渉が長引くケースもあります。
相手に過失があるのにこちらの責任にしてきたり、必要以上の賠償金を引き出そうとしたりするケースもあるため、相手との交渉はプロに任せたいところです。
自分で直接交渉するのは、時間もかかりますし、精神的な負担も大きいです。示談交渉サービスをつければ、安心して保険会社のプロに任せることができるでしょう。
7.弁護士に相談したい
自分が加害者になってしまった時は示談交渉サービスを利用すると良いのですが、問題は被害者になった時です。
示談交渉というのは、自分に賠償責任がある時ですから、被害者になった場合は示談交渉を行うことはできません。
もし被害者になってしまい、相手が補償金をできるだけ少なくしようと交渉してきた時、こちらが頼れるのは弁護士です。ですので、示談交渉サービスとは別に、弁護士費用特約をつけておくと安心です。
8.ロードサービスの有無
通勤・通学で毎日自転車を利用する人や、サイクリングなど自転車で遠くに行くことが多い人は、ロードサービスをつけておくことをおすすめします。
ロードサービスをつけておくと、たとえば自転車が故障したり、タイヤがパンクして動かなくなった時でも、希望した場所まで運んでくれます。
なお、保険商品によって運んでくれる距離に違いがありますので、加入前にきちんと確認してください。
9.充実したサポート体制
自転車事故の補償だけでなく、オプションがつけられたり、直接自転車とは関係のない医療相談サービスなどがついている保険もあります。
自転車事故があった時以外に、保険に何を求めるのかはその人次第です。
十分なサポートがついていることで安心したい人は、傷害保険や個人賠償責任保険以外の部分も比較してみてください。
自転車購入から1ヶ月過ぎた人へおすすめの自転車保険「ペダルワン」
自転車保険が多すぎて、どれに加入したら良いかわからないとお悩みの方へ、トライアングル少額短期保険の「ペダルワン」をご紹介します。
ペダルワンは選びやすい3つのパターンをご用意
あれこれとたくさんのパターンがあると、自分に適したものがどれなのかわからず、選びにくいと思います。
ペダルワンではわかりやすく3つの加入パターンをご用意しています。
【パターン1:損壊・盗難プラン】
自転車の事故による本体の損壊と自転車の盗難を補償するプラン
【パターン2:傷害・賠責プラン】
自転車に乗っている時の事故による死亡、後遺障害、入院、通院と、自転車事故を起こした時の賠償責任を補償
【パターン3:損壊・盗難プラン+傷害・賠責プラン】
パターン1とパターン2を組み合わせたプラン
ここまでご説明してきた、自転車事故を起こしたときに必要な補償を考えますと、パターン2またはパターン3がおすすめです。
通常、自転車の保険というとパターン2のケースが多いのですが、ペダルワンのパターン3であれば、自転車本体の損害や盗難まで補償されます。
非常に手厚い補償内容となっていますので、万が一の時でも安心です。
インターネットで申し込みが完結する
ペダルワンは、インターネットで申し込みができます。保険料のシミュレーションをぜひ試してみてください。
保険料と補償のバランスを見ながら、シミュレーション後にそのままお申し込みいただけます。
手続きはすべてインターネットで完了しますので、店頭窓口まで足を運んでいただく必要はありません。
自転車購入から3年以内なら加入が可能
自転車保険の中には、自転車の購入後1ヶ月以内でないと加入できない保険も多く、購入時に自転車店ですすめられた保険にそのまま加入してしまう方もいます。
しかしペダルワンは、購入後3年以内なら加入が可能です。購入から時間が経ってしまい、なかなか思うような保険料の保険が見つからないとお困りの方も、ぜひご検討ください。
自転車保険のおすすめに関するよくある質問と回答(Q&A)
自転車保険についてみなさんが疑問に思っていること、わからないとお困りのことについて、回答をまとめました。
自転車保険の加入は義務ですか?
自転車保険の加入義務については、自治体ごとに条例で定められています。2023年4月時点で義務化されているのは32都府県、努力義務とされているところが10道県あります。
これらの地域に住んでいる人はもちろん、通勤・通学で自転車を利用してやってくる人、観光目的で訪れて自転車に乗る人も含まれることがあります。
ですので、自分が住んでいる地域では義務化されていなくても、義務化されている地域で自転車に乗る場合は加入義務があるということです。
ただし、義務化されている地域で自転車保険に加入していなくても、今のところ罰則規定はありません。
自転車保険はなぜ義務化されたのですか?
交通事故の件数自体は減少傾向にあるものの、交通事故全体に占める自転車事故の割合は依然として高いです。
自転車事故を起こした場合の損害賠償が高額になるケースが発生していることから、自転車事故が起きた際の被害者の損害の補償だけでなく、加害者側の経済的な負担を少しでも軽くするため、自転車保険の加入を義務付ける自治体が増えています。
全国で半数以上の自治体が加入を義務づけており、この傾向は今後も続くでしょう。
自転車保険に加入しないとどうなりますか?
自転車保険が義務化されたとはいっても、罰則規定はありません。ですから、加入しなからといって何かペナルティがあるわけではありません。
しかし、これまでの裁判を見ますと、自転車事故を起こして、他人にケガをさせた場合や死亡させてしまった場合、9,000万円を超える高額な賠償を命じる判決も出ています。
事故を起こした場合の賠償金は一般の人が支払いできる金額ではないので、保険に加入している方が安心です。
自分の自転車ではなくレンタサイクルに乗る場合も保険の加入は必要ですか?
自転車保険が義務付けられている地域で自転車に乗るなら、それが自己所有のものではなくレンタサイクルであっても、保険に加入すべきです。
保険の加入義務は自転車の所有に関わらず、「自転車に乗ること」自体で発生します。観光でレンタサイクルを利用する際も、その自治体の条例が適用されます。
保険に加入せずに事故を起こし、他人に損害を与えた場合、レンタサイクルであっても当然ながら賠償責任を負うことになります。
自転車保険と個人賠償責任保険の違いはなんですか?
自転車保険の多くは、傷害補償と個人賠償責任補償を組み合わせた内容となっています。
傷害補償は自分自身のケガに備えるもの、個人賠償責任補償は他人への損害を補償するためのものです。自転車事故で相手にケガをさせた場合だけでなく、日常生活の中で他人になんらかの損害を与え、賠償責任を負ったときに賠償金を支払うことができます。
個人賠償責任保険とは、普段の生活の中で他人に損害を与えてしまった時に、その損害を補償する保険です。ケガだけでなく、物を壊したり、水漏れ等で住宅に損害を与えた場合なども含まれます。
自転車保険がカバーしてくれる家族の範囲はどこまでですか?
自転車保険の多くが、被保険者と「生計を共にする同居の家族」までを補償の範囲内としています。
たとえば、世帯主が加入すれば、一緒に暮らしている配偶者や子供が事故を起こした場合も補償が受けられるということです。
ですので、家族ひとりひとりが加入する必要はありません。
また、子供に関しては、未婚で生計を共にしていれば同居していなくても補償されるケースがあります。たとえば、実家を出て親から仕送りを受けながら大学に通っているケースなどです。
ただし、補償の範囲は保険会社によって異なります。事前によく確認してください。
自転車保険に加入する際に気をつけるべきことはありますか?
自転車保険は各社で様々な特徴がありますから、保険料の安さだけで選ばないことです。自分が本当に必要としている補償が受けられるのか、よく比較してください。
それらの保険で自転車事故の賠償責任補償もカバーできる場合がありますので、補償内容がかぶらないようにすることが大切です。
自転車保険の保険料はそこまで高額ではありませんが、同じ補償の保険に二重に入るのは保険料がもったいないです。
自転車を買い替えたら、その都度保険に入り直さないといけませんか?
自転車保険は、自転車本体にかけているものではなく、所有者または乗る人にかかっているものです。
自転車を買った時だけでなく、もらったり借りたりした時でも加入の必要はありますが、一度加入すれば、買い替えるたびに新たに加入する必要はありません。
ですので、2台、3台と自転車を増やしたとしても、その分加入する必要はなく、所有台数に応じて保険料が増えるものでありません。
自転車保険は自分のケガと加害者になった時の補償をカバーする保険
自転車で事故を起こし、人に損害を与えてしまった場合、賠償金額が高額になることから、自転車保険への加入を義務付ける自治体が増えてきました。
義務とはいっても、未加入で罰則規定があるわけではありませんが、万が一のことを考えると、加入しておくべき保険です。
自転車保険の選び方についても解説しましたので、できるだけ保険料を安くしたい、満期返戻金が受け取れるタイプが良い、示談交渉サービスをつけたいなど保険に求めるものを明確にしてから比較をしてみてください。
自転車保険は、自分のケガなどに備える傷害補償と、他人への損害を賠償する個人賠償責任補償がついています。すでに加入している保険と補償内容がかぶらないか、確認してから加入しましょう。